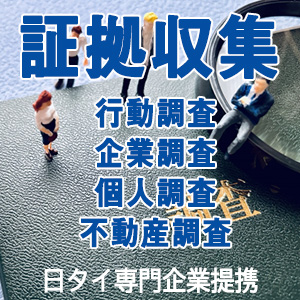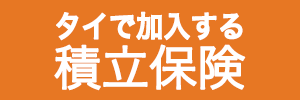- Home
- コラム, 戸島大佐の「在留邦人の危機管理」
- 【再録】戸島大佐の「在留邦人の危機管理」FILE No. 10:薬物の主な種類と症状①
【再録】戸島大佐の「在留邦人の危機管理」FILE No. 10:薬物の主な種類と症状①
- 2025/5/5
- コラム, 戸島大佐の「在留邦人の危機管理」
―― タイで最も使用量が多いヤーバー ――
数ある薬物の中で、タイで最も使用量が多いのがヤーバー。以前はヤーマーと呼ばれていたが、20年以上前にヤーバーと名を変えた。ヤーは「薬」、マーは「馬」の意味。バーはいわゆる「バカ」の意味で、「バカ薬」と訳す日本語を見かけることがあるが、もっとていねいに訳せば「凶薬」となろう。昔も今も、長距離トラックドライバーの眠気覚ましとしての薬、というイメージが強い。
ヤーバーはアンフェタミン系覚醒剤の一種で、「アンフェタミン硫酸塩」「メタンフェタミン」「メタンフェタミン塩酸塩」が配合されている。長距離トラックドライバーほか、タクシードライバー、夜の仕事の女性、ナイトライフを楽しむ若者による乱用が多く見られる。前回の「FILE No. 9:日本人による薬物犯罪」と重複する部分があるが、日本人はたいてい夜の女性から渡されることが多い。「疲労回復のサプリ」程度で受け取って摂取、そのうち止められなくなるというパターンだ。ほか、歓楽街で欲しそうな顔をしていれば、売人が目ざとく見つけてさり気なく話しかけてくる。
錠剤はバンコク辺りでも数百バーツで入手できる。地方に行けばもっと安いだろう。アイスのような結晶・粉末状態のものもある。そもそもアイス(タイ語でヤー・アイス)もヤーバーの一種。いずれも日本語でシャブと総称できる。原料は麻黄という植物から抽出される成分。製造工程で強い臭いを発するため個人で作ることは困難であり、地域住民を取り込んだ組織での密造となる。
「疲労回復」「疲れ知らず」のための薬だけあって、服用すると元気が出る。しかし効力が切れると脱力感、疲労感、倦怠感に襲われる。中毒になると精神的に落ち着かなくなり、「誰かに命を狙われている」という強迫観念にとらわれる。そのような言動を繰り返すことによって尻尾を出し、常習者であることを知られてしまう。
薬物に関してはタイでも罰則が厳しく、警察の取り締まりも決して疎かではないが、とにかく人数が多いので全てを厳しく処するのが困難。初犯などは罰金刑で済ませることもある。しかし一度薬に手を出すと決して止めることはできず、必ず再犯となる。在留邦人は自ら薬に手を出さずとも、そのような薬物常習者と接する機会が少なくない。
* 独り言が多い
* 言動が落ち着かない
* 目やにが多い、目が潤んでいる
といった人物には近づかないことが大事だ。相手は常に、「周囲の全ての人間が敵」という恐怖の世界の中で生き、凶器さえ持ち歩いている危険がある。
戸島国雄
日本の元警視庁刑事部鑑識捜査官、元似顔絵捜査官、タイではタイ警察から警察大佐の階級を与えられる。これまでに4冊、日タイの事件・捜査に関する本を執筆、テレビ出演も多数。現在、日本に帰国中。
再録:過去に掲載して人気が高かったコラムを再アップしています。