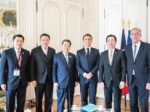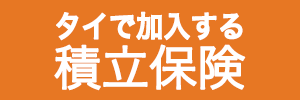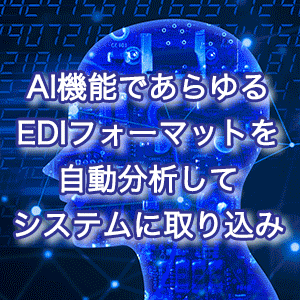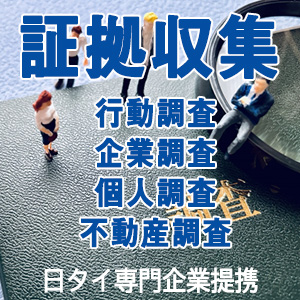【タイ】10月13日付けのタイ英字紙バンコクポストが、バンコクの屋台についての解説記事を掲載している。バンコク都庁(BMA)が都心部ルムピニー公園横に開発中の「ルムピニー・ホーカーセンター」をめぐり、屋台の存続が焦点となると報じている。
—
バンコクの街並みを彩ってきたのは、長年にわたり歩道を埋め尽くしてきた屋台や食堂だ。中華鍋の音、プラスチック椅子に腰掛ける人々、夜更けまで続く談笑は、都市のリズムそのものを形づくってきた。都民にとっては日常の鼓動であり、観光客にとっては食の冒険でもある。
しかし、その魅力の裏側には常に、「文化と秩序」と「生計と法規制」という課題が横たわってきた。この相互関係は数十年にわたり都政を左右してきたが、BMAは歩道の再整備に向けて新たな一歩を踏み出そうとしている。
今年2月に実施されたタイ国立開発行政研究院(NIDA)の世論調査によると、バンコク都民1319人のうち9割以上が屋台で食事をした経験があると回答。利便性や安さを評価する声が多い一方、59%は「幅の広い歩道に限定すべき」と答え、13.8%は全面禁止を支持した。3分の1は「問題は永遠に解決しない」との考えを示した。
都にとって、両立の模索は今に始まったことではない。歴代知事は歩行者空間を取り戻しつつ、生活の糧を奪わない方策を探ってきた。2016年にはスクムパン・ボリバット元知事が、ラーチャプラソン界隈からスクムビット界隈にかけての都心部で、非公認の屋台営業を全面的に排除。都職員と国軍の協力により、都内23区で1万人以上の屋台が立ち退きを迫られた。
「2016年の措置で私たちの生活は一変しました」と語るのは、かつてパトゥムワン区サーラシン通りで麺屋を営んでいたパーニッサラー・ピヤソムロートさんだ。「サーラシン通りの屋台街はギネス記録に登録される直前でしたが、実現しませんでした。私たちは何も問題を起こしていないのに、(都政の)犠牲を強いられました」。
その後、彼女らはルムピニー公園前の空き地に移動させられたが、売り上げは大幅に減少した。それでも多くの店主は営業を続けている。「スペースも席数も減りましたが、同じ収入を得るために皆が必死に働いています」と、鍋料理店を営むプラパーポーン・アナーブットさんは話す。
こうした中、BMAは新たな施設、「ルムピニー・ホーカーセンター」を開発中だ。屋台営業を専門施設に集約し、秩序立てて運営する試みだ。
建設は6月に始まり、来年2月の完成を予定。環境に配慮したオープンエア型の設計で、1区画2平方メートルの屋台を1交代88店舗ずつ配置。午前5時~午後4時、午後4時~深夜0時の二部制で、早朝の公園利用者から夜食客まで幅広く取り込む。
「この施設は衛生面や安全性を高めるだけでなく、低所得層の生活支援にもつながります」と、エークワルンユー・アムラパラーン都庁報道官は説明する。テナント対象は、サーラシン通りの再編で影響を受けた元屋台主が優先される。
建物は自然換気を採用し、向かいのチュラーロンコーン病院の景観に配慮して屋根の色を抑え、撤去した大木は再び植え戻す計画だ。出店資格はタイ国籍を持ち、福祉カード保持者または年収18万バーツ以下の人に限定。契約は1年ごとに更新される。
都庁は、「都心のビジネス街に屋台専門のセンターを設けるのは国内初」と強調。歩行空間の改善や公共空間の安全確保、高齢者や障害者に優しい都市づくりの一環と位置づけている。
すでに一部の区では、民間と連携した小規模な「ミニ屋台センター」が整備され、界隈の勤め人向けに安価な食事を提供している。今回のモデルはシンガポールのホーカー制度を参考に、規制、共同施設、共有の食事空間を組み合わせたものだという。「一部の屋台は大通りから裏道に移らざるを得ないかもしれません。秩序維持と生計確保の両立は常に難しい課題です」とエークワルンユー報道官は話す。
屋台主にとっては、期待と不安が交錯する。「合法的に営業できるチャンスですが、家賃や客がついてきてくれるか心配です」とパーニッサラーさん。一方、「新しい施設は雨や停電の心配もなく、トラブルも減るでしょう」と、50バーツ食べ放題の店を営むジラッポン・パーンパイさんは話す。
歩道の屋台から組織的なフードハブへ。バンコクの変革は単なる政策転換にとどまらず、世界的に知られる「屋台の街」の味を失わずに近代化できるかどうかの試金石となる。ある人にとっては安定への道であり、別の人にとっては生存競争の場でもある。それでも「バンコクの屋台文化は消えるのではなく、進化する」という希望は残されている。